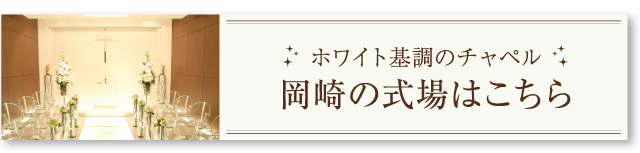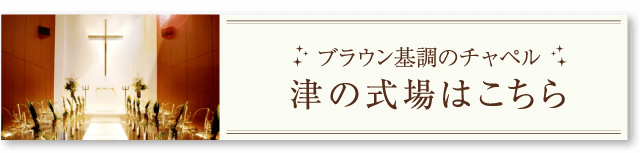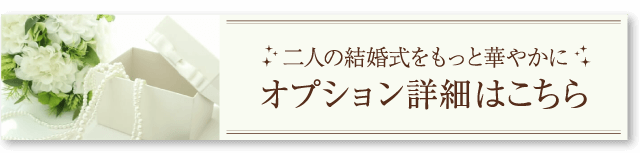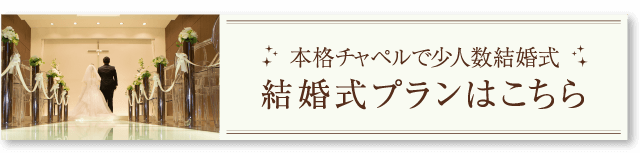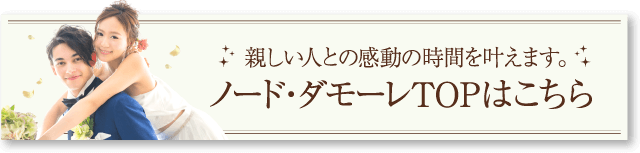結婚について考えたことはありますか。
結婚は将来を考える上でとても大切なことですよね。
結婚となると、「大切な人と一生を共にしたい」、「幸せな家庭を築きたい」という幸せなイメージがあります。
しかしその反面、結婚式にかかる費用が高く、金銭的な不安もあることでしょう。
そこで今回は、結婚助成金について、申請方法や注意点を紹介します。

□結婚助成金とは
一度は耳にしたことがある人もいるであろう結婚助成金ですが、結婚助成金とは地方自治体から貰うことができる援助金です。
現在の日本は、少子化が進んでおり、2019年には、出生数が約86万にという数字で過去最低を記録しました。
結婚助成金の支給制度は、現在の日本における少子化が進んでいる状況を打破するために始められた制度です。
結婚をする際は、新生活が始まり、さまざまな費用が必要になります。
また、出産や育児などもあり、結婚後の新生活には金銭面の不安が残ります。
そのような不安を払拭して、地方公共団体が資金面において、結婚、妊娠、出産さらには子育てをしやすい環境を作っていくために補助をしてくれます。
□結婚助成金の申請方法とは
結婚助成金を受け取る際には、書類を提出し助成金受取の申請が必要となります。
地方自治体に助成金の申請をして、その後やっと結婚助成金を貰えます。
ここからは、申請方法についてご紹介します。
*結婚助成金の申請の際に必要な書類
申請の際にはさまざまな書類の提出が必要になります。
主に申請には、入籍後の住民票・ 補助金交付申請書・ 補助金交付請求書・ 婚姻後の戸籍謄本・ 新居の住居費や引越しの領収書・ 市県民税の滞納がないことを証明する書類・賃貸借契約書などの新居に関する書類・ 世帯の所得証明書などが必要です。
しかし、地方自治体によって必要な書類は少しずつ異なるため、それぞれの地方自治体のホームページで確認しておくことが確実でしょう。
また、自治体のホームページでダウンロードが可能な場合もあるので、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。
*結婚助成金の申請先と申請時期
結婚助成金は申請しないと受け取ることはできないため、必ず地方自治体に申請しておきましょう。
結婚助成金制度は国が行っている制度ですが、申請先はそれぞれの自治体の窓口であるため、申請は地方自治体に申請する必要があります。
また、結婚助成金を受け取るための申請には期間が設けられます。
自治体によって申請期間は異なるため、注意が必要です。
4月から3月までの年度初めから年度末ぎりぎりまで申請期間が設けられる自治体もありますが、年度の途中で締め切りを迎える自治体もあるので注意が必要です。
年度ごとに申請する助成金制度なので、婚姻や引っ越しが年度をまたぐことが無いようにしましょう。
どの自治体であれ、自治体に住んでいて、新しく婚姻届を提出することで対象となります。
□結婚助成金を申請するときに注意すること
結婚助成金を受け取るの際には、先ほど述べたように、必要な書類をそれぞれの自治体の結婚助成金の申請期間に提出することが必要です。
ただし、この条件を守っていても結婚助成金を利用できないケースがあるので、ここで紹介する注意点を確認しておきましょう。
まずは、結婚助成金が利用できる地域とできない地域についてです。
結婚助成金利用しようと思うと、地方自治体に申請をしないといけません。
しかし、全ての自治体がこの制度を取り入れているわけではないのです。
令和3年8月では538もの自治体で結婚助成金制度が導入されていますが、残りの約1,200もの自治体では導入されて生ません。
利用するには、まず自治体が結婚助成金制度を導入されているか確認してみましょう。
次に、結婚助成金の受取に伴う条件についてです。
結婚助成金を受け取る際に、ある条件が設けられています。
1つ目は、年齢制限です
現在では、婚姻日の夫婦両方の年齢が39歳以下の夫婦を対象としています。
2つ目の制限が、所得制限です。
世帯で所得合計が540万円未満の夫婦でなければ結婚助成金は受け取ることができません。
このように年齢制限と所得制限の2点によって対象者を絞っているため、上記の条件に当てはまっているか確認しましょう。
以前は、年齢制限は34歳以下、所得制限も世帯で340万円未満の夫婦のみという制限でしたが、少子化という現状を打破するために条件が緩和されました。
また、制度そのものを利用したことが無ければ、再婚者も申請することが可能です。
最後に、結婚助成金の決められた使い道についてです。
対象は、結婚式や家具などの新婚生活の全てを援助するものではなく、新居の住居費と新居への引越し費用のみです。
結婚助成金は新生活の力添えとして給付されています。

□まとめ
今回は、結婚助成金についてお話ししました。
結婚助成金を知らなかった人や、申請方法が分からなかった人などは、それぞれの自分の地域の自治体のホームページから結婚助成金について調べて、申請を検討してみてはいかがでしょうか。
新婚生活で残る金銭面不安を払拭するためにも、結婚の際には、結婚助成金を利用してみましょう。