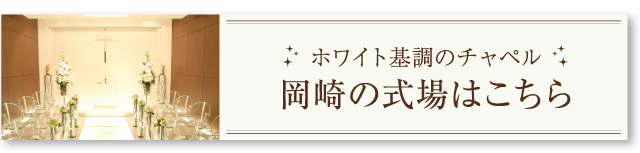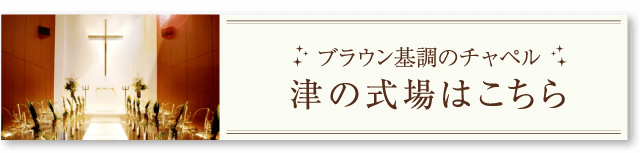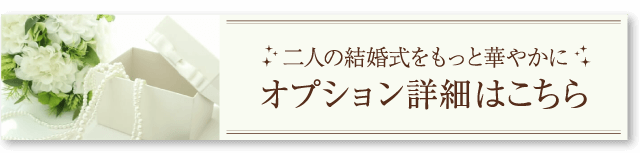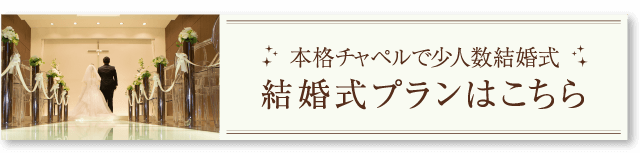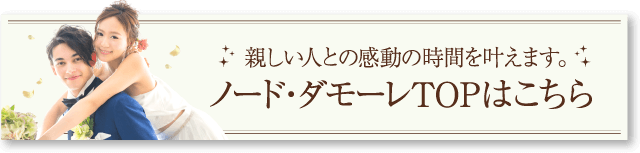結婚すると、これからの生活費や引越し代など様々な場面でお金がかかるものです。
そうなると、新生活への楽しみがある反面、費用に関して不安を抱えることになります。
そこで今回は、結婚するともらえるお金と申請方法についてご紹介します。

□結婚するとお金がもらえる?
これから結婚する方は、新生活に期待が膨らむ反面費用に関する不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そんなときに知っておいてもらいたいのが、結婚助成金です。
「結婚するともらえる助成金」として話題になったこの助成金ですが、必ず誰でも受け取れるものではなく、受け取ることができても自由に使えるわけではありません。
ここでは結婚助成金についてご紹介するので、正しい知識を身につけていきましょう。
*結婚新生活支援事業補助金とは
これは、内閣府が少子化対策の一環として世帯の負担軽減のために始められた制度で、国から結婚によって新生活をはじめる際に必要な費用が支給されます。
条件を全て満たした上で役所へ申請すると、一世帯あたり最大60万円までの補助金を受け取れます。
費用面で不安を抱えていると、60万円の支給があるだけで楽になるでしょう。
ただし、この制度は、すべての世帯が支給対象になるわけではないことに加え、条件を満たす必要があります。
とはいえ、対象世帯を増やすと同時に条件を緩和する動きがみられているため、これから結婚を考えている方は最新の情報を集めておくことをおすすめします。
支給された場合、新居の家賃、新居の敷金・礼金、新居の共益費や仲介手数料・引越の際にかかる運送費用などの諸経費などに使用できます。
何にでも使えるわけではないので、注意してください。
*結婚新生活支援事業補助金の対象
前提として「結婚新生活支援事業」を実施している自治体に住んでいる方のみがこの結婚助成金を受け取れる対象になります。
つまり、対象の自治体に住んでいなければ、いくらそのほかの条件を満たしていても支給の対象にはなりません。
現在の対象条件として、入籍した日が2人とも39歳以下であること、世帯年収が約540万円未満であることなどの条件が挙げられます。
先ほどご紹介したように、対象世帯を増やすと同時に条件を緩和する動きがみられているため、対象の自治体に住んでいるが条件を満たしていないという方も、今後の展開に注目しておくことをおすすめします。
また、上記の条件の中で、年収面のみ条件に当てはまらないと判断したカップルは、今一度収入を確認しなおしましょう。
ここにおける「年収」の意味は、「収入」ではなく「所得」を指しています。
「所得」とは給料明細に記される月々の収入から、給与所得控除を差し引いた金額のことです。
そのため、計算し直すと条件を満たす可能性もあるので、給与明細を確認して計算し直すことをおすすめします。
さらに、寿退社をする場合は、収入があった数ヵ月分は世帯年収としてカウントされない場合があるため注意してください。
□結婚助成金の申請方法とは?
申請する際は、証明書を揃えて申請書類に必要事項を記入して費用明細や領収書を用意します。
自治体によって必要な書類は異なりますが、婚姻を証明する書類や入籍後の戸籍謄本、市税の滞納がないことの証明などが必要です。
また、自治体ごとに記入フォーマットがあるので、記入する必要があるものはあらかじめしっかりと記入・捺印しておきましょう。
全ての書類を揃えたら市区町村の役所に持って行くか、郵送して申請してください。
□結婚助成金の申請時の注意点について
最後に、結婚助成金の申請時の注意点についてご紹介します。
何かとお金のかかる結婚助成金ですが、申請時には以下の3点に注意しましょう。
1つ目は、支払いが完了しているものが対象であることです。
取得費・賃料・敷金・礼金・共益費など新居の住居費を支払った証明となる領収書といったような支払ったことが分かる書類が必要であり、これから購入するものに関しては助成の対象外となっている。
2つ目は、すべての市区町村で実施しているわけではないことです。
対象地域でなければこの助成金は受けられないため、対象地域であるかどうかは各自治体に確認しておきましょう。
3つ目は、新居への引っ越し費用でも対象外のものがあることです。
引越しに伴うレンタカー代や不用品処分代などは対象外です。
なお、先ほどご紹介したように対象世帯を増やすと同時に条件を緩和する動きがみられているため、ここでご紹介した注意点は改正される可能性があります。
年度によって大きくルールが変わる可能性もあるため、随時最新の情報を確認するようにしてください。

□まとめ
今回は、結婚するともらえるお金と申請方法についてご紹介しました。
結婚すると必ずもらえるわけではなく、この助成金を受け取るための条件を満たしている必要があるので注意してください。
自治体によって必要な書類や申請条件などが異なるため、申請前に確認しておくことをおすすめします。