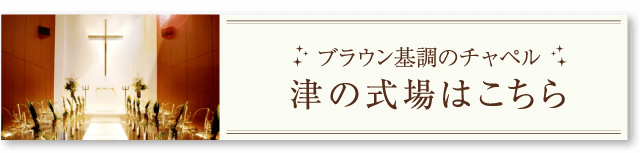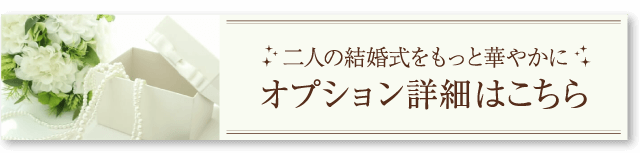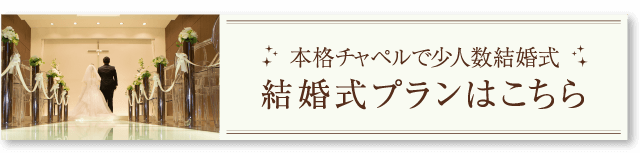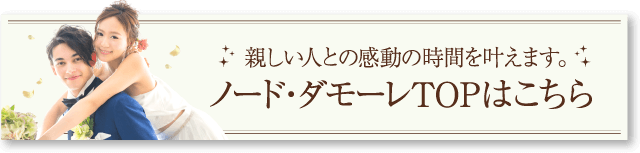結納、大切な儀式を終え、次はお返しのことに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
結納のお返しは、地域や家庭によって風習が異なり、金額や品物、タイミングなど、さまざまな疑問が湧いてくるのも当然です。
今回は、結納のお返しに関する基本的な流れから、相場、マナー、具体的な方法、そして現金か品物か、タイミング、結納金がない場合の対応など、様々なケースについて解説します。
結納金のお返し!基本的な流れと種類
結納返しが必要な理由と、しない場合の選択肢
結納返しは、男性側から女性側へ贈られた結納品や結納金に対するお礼として行われるものです。
感謝の気持ちを表す行為であり、今後の良好な関係を築く上で重要な役割を担っています。
しかし、近年では結納そのものを簡略化したり、行わないケースも増えているため、結納返しを必ず行わなければならないという決まりはありません。
結納金を受け取らなかった、もしくは両家で「お返しは不要」と合意している場合は、結納返しは不要です。
ただし、結納を行った場合は、お礼の気持ちを示すことが一般的とされています。
結納返しの種類
結納返しには、関東式と関西式があり、その形式によって風習が異なります。
関東式では、結納品の半額程度を返す「半返し」が一般的です。
現金の場合、結納金の半額、品物であれば同等の価値のものを用意するのが一般的です。
一方、関西式では、結納返しを行わないケースが多く、行う場合でも、結納金の1~2割程度の金額や品物が一般的です。
これは、関東では両家が同格であるという考え方、関西では男性側が格上であるという考え方の違いが影響していると考えられます。
地域差だけでなく、家庭によって異なる場合もありますので、事前に両家で話し合って決めることが重要です。
結納返しにおける一般的なマナーと注意点
結納返しは、単なるお礼の行為ではなく、今後の良好な関係を築くための重要な儀式です。
現金で返す場合は、祝儀袋を使用し、「御袴料」と表書きします。
金額は縁起の良い数字(3、5、7など)を選び、4や9は避けるのが一般的です。
品物で返す場合は、風呂敷で丁寧に包みます。
いずれの場合も、相手への感謝の気持ちと、今後の良好な関係への期待を込めて、丁寧な対応を心がけることが大切です。

結納金のお返しの相場と具体的な方法
結納返しの相場
結納返しの相場は、地域や結納金の額によって大きく異なります。
金額は、30万円、50万円といったキリの良い数字が好まれます。
品物を選ぶ場合は、10~20万円程度のものが一般的ですが、これも結納金の額や、贈る品物によって大きく変動します。
大切なのは、相手に失礼がない程度に、両家の経済状況を考慮した金額にすることです。
結納返しの品物選び
結納返しの品物としては、腕時計、スーツ、バッグ、家電製品などが挙げられます。
相手が喜んでくれるものを選ぶことが大切です。
実用的なもの、長く使えるものが好まれます。
また、相手方の好みやライフスタイルを考慮し、事前に相談するのも良い方法です。
近年では、新生活に役立つ家電や、趣味に関連する品物など、個々の事情に合わせた品物を選ぶケースも増えています。
結納返しの現金の渡し方と注意点
現金で結納返しをする場合は、祝儀袋を使用し、「御袴料」と書き、水引は「あわじ結び」を選びます。
新札を使用し、丁寧に包んで渡すことが大切です。
渡す際には、感謝の気持ちを伝える言葉とともに、今後の良好な関係への期待を込めた言葉を添えると良いでしょう。
結納返しを渡す最適なタイミング
結納返しを渡すタイミングは、結納当日、結納後、新居への引っ越し時など、様々な選択肢があります。
結納当日に行う場合は、結納と同時に行うことが一般的です。
結納後に改めて渡す場合は、結納後から結婚式までの間に行うのが一般的です。
新居への引っ越し時に渡す場合は、新生活のスタートを祝う意味合いも加わります。
どのタイミングを選ぶかは、両家の都合や状況に合わせて決定しましょう。

まとめ
結納のお返しは、感謝の気持ちを表す重要な儀式です。
しかし、必ずしも行わなければならないものではなく、地域や家庭の習慣、経済状況などを考慮し、両家が納得できる方法を選ぶことが大切です。
現金か品物か、金額やタイミングなども、事前に十分に話し合い、お互いに気持ちの良い形で結納のお返しを終えられるよう心がけましょう。
地域差や家庭によって様々なケースがあることを理解し、柔軟に対応することが重要です。
事前に十分に話し合い、お互いに気持ちの良い形で結納のお返しを終えられるよう心がけましょう。