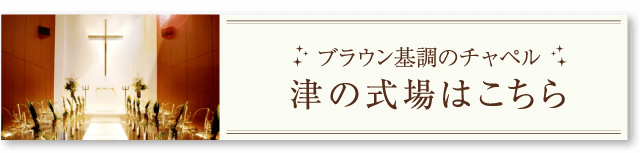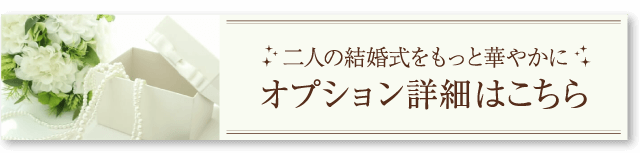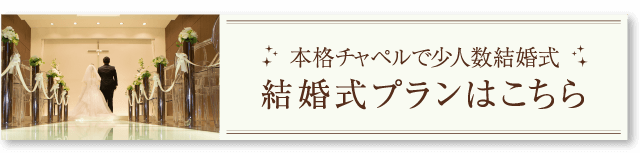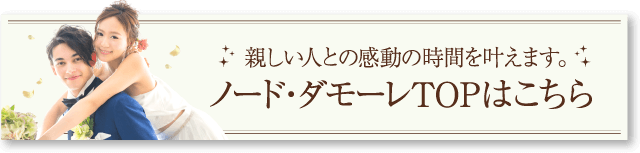初めて略式結納を行うカップルにとっては、流れや準備、マナー、費用など、わからないことが多く不安もつきものです。
今回は、略式結納の流れをステップごとに丁寧に解説します。
準備やマナー、費用についても具体的にご紹介しますので、安心して結納に臨めるようサポートできれば幸いです。
略式結納の流れをステップごとに解説
結納品の飾り付けと着席方法
結納品は、両家の代表者が一緒に飾り付けるのが一般的です。
和室の場合は床の間、またはその前方、洋室の場合はテーブルの中央に飾ります。
男性側は右側、女性側は左側に飾り付けるのが一般的ですが、必ずしも厳格なルールではありません。
大切なのは、両家で事前に話し合って決めることです。
着席方法は、入口から遠い方が上座となります。
床の間がある場合は、床の間の前に上座を設けます。
席順は、男性側(新郎、父親、母親、兄弟姉妹など)、女性側(新婦、父親、母親、兄弟姉妹など)と、それぞれ家族構成に応じて並べます。
はじまりの挨拶と進行役について
はじまりの挨拶は、通常男性側の父親が行います。
しかし、緊張する場合は、男性本人や、両家の父親が共同で行うことも可能です。
また、スムーズな進行のために、事前に挨拶の内容をメモに書き留めておくことをお勧めします。
挨拶では、結納の目的と感謝の気持ちを述べ、和やかな雰囲気で始めることが大切です。
進行役は、男性側の父親が務めることが多いですが、話しやすい方、または事前に役割分担を決めておくことで、よりスムーズに儀式を進めることができます。
結納品の納め方と口上例
結納品の納め方は、関東式と関西式で異なります。
関東式では、男性側から女性側へ、その後女性側から男性側へと結納品を贈り合うのが一般的です。
関西式では、男性側から女性側へのみ贈り合うのが一般的です。
結納品は、目録と共に丁寧に運び、受け取る側へ感謝の気持ちを伝える口上を述べます。
口上は、事前に準備しておくと安心です。
以下に、口上例をいくつかご紹介します。
男性側(納める際):「本日は誠にありがとうございます。
〇〇家より、結納の品でございます。
末永くお幸せに暮らされますよう、お納めください。」
女性側(受け取る際):「ありがとうございます。
〇〇家より賜りました結納の品々、大切に受け取らせていただきます。」
受書と結納返しのやり方
結納品を受け取った側は、受書を書き、男性側に渡します。
受書には、受け取った結納品を一覧で記載し、感謝の気持ちを丁寧に記します。
結納返しは、関東式では結納金の半額程度、関西式では結納金の1割程度が一般的ですが、近年は両家で話し合って金額を決めるケースが増えています。
結納返しは、結納品と同様に、感謝の気持ちを込めて丁寧に渡します。
婚約記念品の披露と締めの挨拶
婚約記念品の披露は、結納品を納め終えた後に行います。
婚約指輪やネックレスなど、事前に決めておいた記念品を交換し、お互いの気持ちを改めて確認する機会となります。
締めの挨拶は、男性側の父親、または両家の父親が共同で行うのが一般的です。
挨拶では、結納が滞りなく終了したことを報告し、今後の良好な関係を誓います。
関東式と関西式の違い
関東式と関西式では、結納品の品目数、納め方、結納返しの有無などに違いがあります。
関東式では、両家から結納品を贈り合うのが一般的で、結納返しを行うのが一般的です。
一方、関西式では、男性側から女性側へのみ結納品を贈り、結納返しは行わない場合が多いです。
結納品の品目も異なり、関東式では9品目が一般的ですが、略式結納では5品目程度に簡略化されることも多いです。
関西式では、地域によって品目が異なります。
事前に両家で話し合って、どちらの形式で行うか、または両方の形式の良いとこ取りをするかなどを決定しましょう。

略式結納に関する必須知識
略式結納に必要なものと費用相場
略式結納に必要なものは、結納金、結納品、受書、婚約記念品などです。
結納品は、関東式、関西式、または両家の地域によって異なります。
費用相場は、結納金、結納品、会場費、食事代などを含め、5万円~30万円程度と幅広いです。
しかし、近年は結納金や結納品を簡略化したり、自宅やレストランで行うことで費用を抑えるカップルが増えています。
ご自身の予算に合わせて、必要なものを選び、費用を抑える工夫をしましょう。
略式結納における服装とマナー
略式結納の服装は、セミフォーマルが一般的です。
女性はワンピースやスーツ、男性はスーツが適切です。
ただし、華美すぎる服装は避け、落ち着いた雰囲気の服装を選びましょう。
マナーとしては、遅刻を避け、言葉遣いに気を配り、相手への配慮を忘れずに、食事の際は箸の持ち方や食べ方にも注意しましょう。
また、結納の最中は私語を避け、真剣な態度で臨むことが大切です。
結納品の意味と選び方
結納品には、それぞれ意味が込められています。
例えば、昆布(子生婦)は「よろこぶ」に通じ、縁起の良いものです。
熨斗(のし)は、鮑(あわび)を伸ばしたもので、祝儀を表します。
これらの意味を理解し、両家の想いを込めた結納品を選びましょう。
略式結納では、必ずしも全ての品目を揃える必要はありません。
大切なのは、両家の気持ちが込められた、心温まる結納品を選ぶことです。
忌み言葉と注意すべき点
結納では、「切る」「別れる」「壊れる」といった、縁起の悪い言葉(忌み言葉)を避けることが大切です。
また、重ね言葉も避けるのが望ましいです。
その他、結納品は風呂敷で包んで持ち運び、持ち帰る際は風呂敷を結びましょう。
これらのマナーを守ることで、結納を円滑に進めることができます。
仲人を立てる場合の流れ
仲人を立てる場合は、進行役を仲人が務め、結納品のやり取りも仲人を介して行われます。
仲人への依頼、挨拶、お礼などを忘れずに、事前に準備しておきましょう。
仲人を通して行うことで、より正式な雰囲気になり、両家の絆を深めることができます。
ただし、近年は仲人を立てない略式結納が主流となっています。

まとめ
この記事では、略式結納について解説しました。
略式結納は現代のライフスタイルに合わせた形式です。
しかし、簡略化されたからこそ、マナーや言葉遣い、相手への配慮を十分に意識することが大切です。