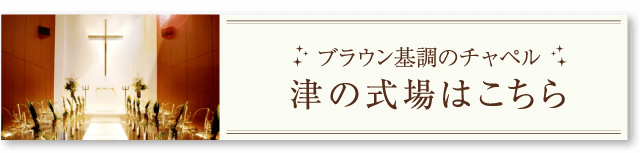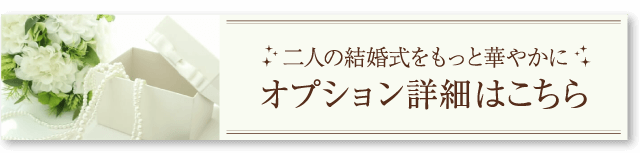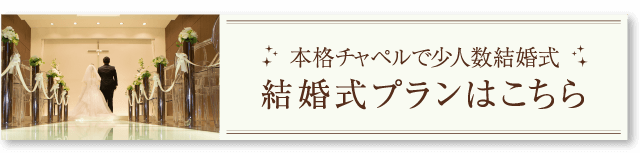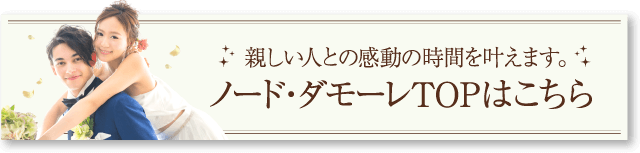結婚式を控えている新郎新婦にとって、ゲストへの交通費負担は頭を悩ませる問題の一つでしょう。
特に、飛行機を利用してくるゲストの場合、交通費が大きく、どの程度負担すべきか迷う方も多いはずです。
結婚式は人生の大切な節目であり、大切なゲストには喜んで参加してもらいたいものです。
しかし、交通費負担は、新郎新婦にとっても大きな負担になる場合があり、適切な金額や渡し方、ゲストへの伝え方など、様々な点を考慮する必要があります。
今回は、結婚式における飛行機代負担のマナーや相場、金額の決め方、ゲストへの伝え方について、具体的な例を交えながら解説していきます。
結婚式の飛行機代負担の相場と基準
結婚式に飛行機を利用してくるゲストへの交通費負担は、新郎新婦側が全額負担するのが理想です。
しかし、状況に応じて、半額負担など、柔軟に対応する必要がある場合もあります。
1: 理想は全額負担
遠方からのゲストには、感謝の気持ちを込めて交通費を全額負担するのが理想です。
結婚式への参加を促し、ゲストに気持ちよく過ごしてもらえるよう、交通費の負担は新郎新婦側がしっかりと行うべきでしょう。
2: 状況に応じて半額負担も検討
しかし、遠方のゲストが多数いる場合や、新郎新婦側の予算が限られている場合は、全額負担が難しいケースもあります。
そのような場合は、ゲストとの関係性や距離などを考慮し、半額負担など、可能な範囲での負担を検討しましょう。
3: 遠方ゲストの交通費判断基準
結婚式に招待するゲストが、どの程度の距離から「遠方」と判断するかは、明確な基準はありません。
一般的には、以下の点を参考に判断するのが一般的です。
・往復の交通費が5,000円以上の場合
・交通費と宿泊費を合わせて20,000円以上の場合
・新幹線や飛行機を利用する場合
これらの基準を参考に、ゲストの状況に応じて、適切な判断を下すようにしましょう。

結婚式の飛行機代負担額の決め方と渡し方
飛行機代を負担する場合、金額の決め方はゲストへの負担を考慮しながら決める必要があります。
全額負担するのか、片道分だけ負担するのか、金額を割り切って1万円や5千円などキリの良い金額にするのかなど、様々な選択肢があります。
1: 金額の決め方
往復の航空券代を参考に全額負担:最も一般的な方法です。
ゲストに負担をかけずに、気持ちよく参加してもらえます。
片道分を負担:全額負担が難しい場合や、ゲストとの関係性によって、片道分だけ負担する場合もあります。
金額を割り切って負担:ゲストへの負担を軽減するため、1万円や5千円などキリの良い金額に割り切って負担する場合もあります。
2: 渡し方
結婚式前に現金書留で送る:事前に金額を伝えて、結婚式前に現金書留で送る方法です。
ゲストに直接渡すよりも、丁寧な印象を与えます。
当日受付で渡す:結婚式当日に受付で渡す方法です。
事前に伝えておけば、ゲストもスムーズに受け取れます。
事前に相談して決める:ゲストと事前に相談し、金額や渡し方について合意しておく方法です。
ゲストの希望を聞き取り、双方にとって納得のいく方法を選ぶことができます。

結婚式の飛行機代負担をゲストへ伝える方法
飛行機代を負担する旨は、ゲストに失礼のないように、事前に伝えることが大切です。
招待状に記載したり、電話やメールで事前に伝えておくのが良いでしょう。
1: 招待状に記載する
招待状に「交通費の一部を負担させていただきます」などの言葉を入れて、事前に伝える方法です。
招待状に記載することで、ゲストへの配慮を示すことができます。
2: 電話やメールで伝える
招待状に記載するスペースがない場合や、金額などの詳細を伝えたい場合は、電話やメールで事前に伝える方法もあります。
電話やメールで伝える場合は、丁寧な言葉遣いを心がけ、ゲストに失礼のないように伝えましょう。
3: 全額負担できない場合は正直に伝える
全額負担が難しい場合は、その旨を正直に伝え、ゲストに理解してもらうことが大切です。
全額負担できない理由を説明し、可能な範囲での負担を提案することで、ゲストとの良好な関係を築くことができます。
まとめ
結婚式に飛行機を利用してくるゲストへの交通費負担は、新郎新婦にとって大きな課題です。
全額負担が理想ですが、状況に応じて、半額負担など、柔軟に対応する必要があります。
金額の決め方としては、往復の航空券代を参考に全額負担する、片道分を負担する、金額を割り切って負担するなど、ゲストへの負担を考慮しながら決めることが大切です。
また、渡し方としては、結婚式前に現金書留で送る、当日受付で渡す、事前に相談して決めるなど、様々な方法があります。
ゲストとの関係性や状況に応じて、適切な方法を選びましょう。
飛行機代を負担する旨は、招待状に記載したり、電話やメールで事前に伝えておくのが良いでしょう。
全額負担できない場合は、その旨を正直に伝え、ゲストに理解してもらうことが大切です。
結婚式は、新郎新婦にとって人生の大切な節目であり、大切なゲストには喜んで参加してもらいたいものです。
交通費負担については、ゲストへの感謝の気持ちを忘れずに、適切な対応をするようにしましょう。