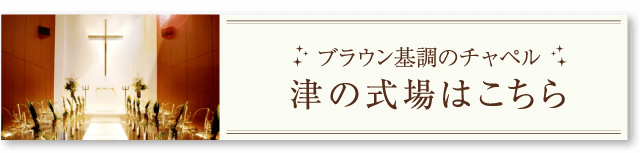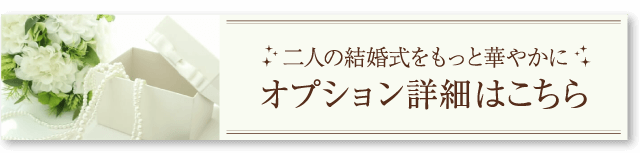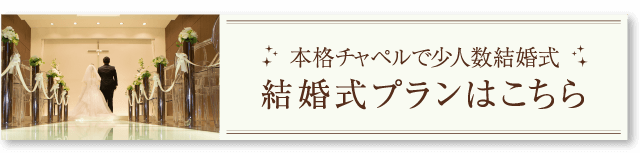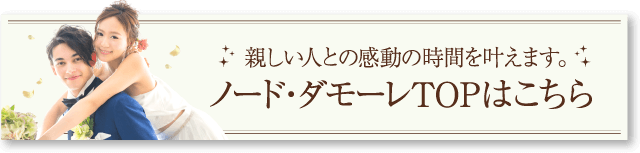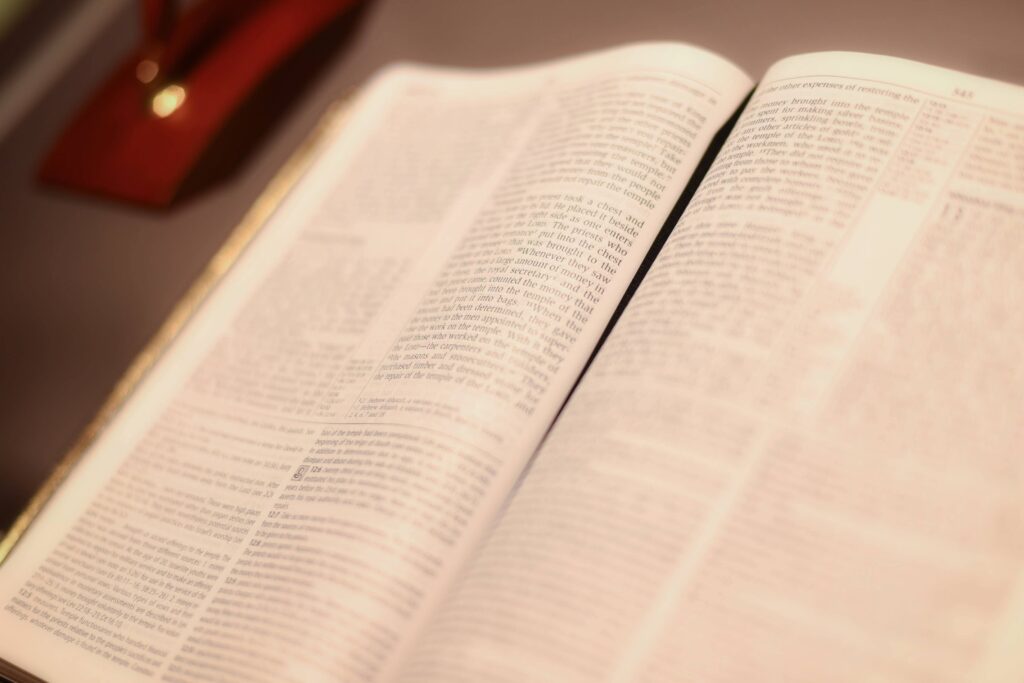結婚が決まり、いよいよ彼の親に結婚の挨拶をしなければならないあなた。
「服装やマナー、手土産など、何を準備したらいいか分からない…」
「結婚の挨拶で好印象を与えたいけど、どこから手をつければいいか不安…」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、彼の親に結婚の挨拶をする際に、好印象を与えるための服装、マナー、手土産選びから当日の流れまで、具体的な方法を分かりやすく解説していきます。
彼の親に結婚の挨拶をする際に、ぜひ参考にしてみてください。
□彼親への結婚挨拶で好印象を与えるための服装とは?
結婚の挨拶は、人生において重要な節目であり、彼の親との良好なスタートを切るための最初の機会です。
そのため、服装には特に気を配ることが大切です。
清潔感があり、上品で清楚な服装は、相手に好印象を与えるだけでなく、あなたの誠実な気持ちを表すことにも繋がります。
では、具体的にどのような服装を選べば良いのでしょうか。
1: ワンピースまたはスカートスーツ
結婚の挨拶には、ワンピースやスカートスーツがおすすめです。
ワンピースは、上品で女性らしい印象を与えやすく、スカートスーツは、きちんと感があり、誠実な印象を与えやすいです。
ただし、デザインや色は、派手すぎず地味すぎないものを選びましょう。
例えば、膝丈のワンピースにブラウスを合わせたスタイルや、シンプルなスカートスーツにブラウスとカーディガンを合わせたスタイルなどがおすすめです。
2: カラー選び
色は、白、ベージュ、薄いピンク、薄いブルーなど、明るいパステルカラーがおすすめです。
これらの色は、清潔感があり、相手に好印象を与えやすいです。
逆に、黒、グレー、濃い赤などの暗い色は、少し重たい印象を与えてしまうため、避けるようにしましょう。
3: アクセサリー
アクセサリーは、シンプルで上品なものを選びましょう。
華美なアクセサリーは、相手に落ち着きがない印象を与えてしまう可能性があります。
ネックレス、ブレスレット、イヤリングなど、1〜2点程度に留め、主張しすぎないものがおすすめです。
4: NGな服装
結婚の挨拶では、以下の服装は避けるべきです。
露出の多い服装
カジュアルすぎる服装(ジーンズ、Tシャツなど)
奇抜な服装(派手な柄、アクセサリーなど)
5: 靴
靴は、ヒールが低く、歩きやすいものを選びましょう。
長時間歩くことを想定し、疲れない靴を選ぶことが大切です。
また、パンプスやローファーなど、きちんと感のある靴を選びましょう。
6: メイク
メイクは、ナチュラルで上品なものを心がけましょう。
濃いメイクは、相手に不快感を与えてしまう可能性があります。
普段通りのメイクでも問題ありませんが、少しだけ華やかさを加える程度にしましょう。
7: 髪型
髪型は、清潔感のあるまとめ髪がおすすめです。
ロングヘアの場合は、アップスタイルやハーフアップなど、顔周りがスッキリ見える髪型にしましょう。
ショートヘアの場合は、ヘアスタイリング剤などで、きちんと感のある髪型にしましょう。

□結婚挨拶のマナーを徹底解説!
結婚の挨拶では、服装だけでなく、言葉遣いや立ち居振る舞いなど、様々なマナーが重要となります。
彼の親に好印象を与え、結婚への承諾を得るためには、基本的なマナーをしっかり押さえておく必要があります。
1: 訪問時間
訪問時間は、事前に彼から彼の親に確認しておきましょう。
基本的には、午後2時〜4時頃が一般的です。
ただし、相手の都合に合わせて、柔軟に対応することが大切です。
2: 手土産
手土産は、必ず用意しましょう。
彼の親の好みや、アレルギーなどを事前にリサーチし、失礼のない手土産を選ぶことが大切です。
一般的な手土産としては、お菓子、果物、お茶などが挙げられます。
また、相手の家に何か困っていることがあれば、それを解決できるような手土産を選ぶのも良いでしょう。
例えば、コーヒーをよく飲むという情報があれば、高級コーヒー豆など、喜ばれる手土産を選ぶことができます。
3: 言葉遣い
言葉遣いは、丁寧で敬語を使うようにしましょう。
特に、初対面の場合は、相手への敬意を払い、丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。
また、相手の名前を呼ぶ際は、必ず「○○様」と呼び捨てにしないように注意しましょう。
4: 立ち居振る舞い
立ち居振る舞いは、落ち着いて、礼儀正しく振る舞うようにしましょう。
特に、初対面の場合は、緊張してしまうかもしれませんが、深呼吸をして落ち着いて、笑顔で挨拶をするようにしましょう。
また、姿勢を正して座り、相手の話に真剣に耳を傾けることが大切です。
5: 会話
会話は、明るく、親しみやすい雰囲気で話しましょう。
ただし、失礼な発言や、プライベートな話題は避けるようにしましょう。
また、相手の話を遮ったり、自分の話ばかりしたりしないように、会話のバランスにも気を配りましょう。
6: 感謝の気持ち
結婚の挨拶の際には、感謝の気持ちを伝えることを忘れないようにしましょう。
特に、結婚の承諾を得られた場合は、感謝の気持ちを込めて、丁寧にお礼を述べましょう。
□結婚挨拶の手土産選びのポイント
結婚の挨拶では、手土産は必須です。
彼の親に好印象を与え、結婚への承諾を得るためには、手土産選びにも気を配ることが大切です。
では、どのような手土産を選べば良いのでしょうか。
1: 彼の親の好みをリサーチする
手土産を選ぶ上で最も重要なのは、彼の親の好みをリサーチすることです。
彼の親がどのようなものを好むのか、事前に彼から情報を得ておきましょう。
例えば、お菓子が好きなら、高級なお菓子や、こだわりのあるお菓子を選ぶことができます。
また、お茶が好きなら、お茶のセットや、お茶菓子など、相手の好みに合わせた手土産を選ぶことができます。
2: アレルギーに注意する
彼の親にアレルギーがある場合は、事前に確認し、アレルギー対応のものを選ぶようにしましょう。
アレルギー対応のものは、事前に調べておく必要があります。
また、アレルギーがない場合でも、万が一、アレルギー反応が出る可能性も考慮し、無添加のものや、シンプルなものを選ぶのがおすすめです。
3: 日持ちするものを選ぶ
手土産は、日持ちするものを選ぶのがおすすめです。
特に、結婚の挨拶は、事前に日時が決まっていることが多いので、日持ちするものを選ぶことで、相手に負担をかけずに渡すことができます。
お菓子、お茶、お酒など、日持ちするものがおすすめです。
4: 渡す際の言葉遣い
手土産を渡す際は、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
「本日はお忙しい中、お時間を作っていただきありがとうございます。
少しばかりですが、ご挨拶に伺いましたので、お受け取りください。
」
など、感謝の気持ちを込めて、丁寧に渡すようにしましょう。
5: NGな手土産
結婚の挨拶では、以下の手土産は避けるべきです。
タブーとされているもの(香典、仏壇用の線香など)
個人の好みが分かれるもの(お酒、タバコなど)
高価すぎるもの(ブランド品など)
安っぽく見えるもの(スーパーで売っているようなお菓子など)

□まとめ
この記事では、彼の親に結婚の挨拶をする際に、好印象を与えるための服装、マナー、手土産選びから当日の流れまで、具体的な方法を解説しました。
結婚の挨拶は、彼の親との良好なスタートを切るための最初の機会です。
この記事を参考にして、自信を持って結婚の挨拶に臨んでください。
彼の親に好印象を与え、結婚への承諾を得ることができれば、その後のお付き合いもスムーズに進むでしょう。
結婚の挨拶は、あなたにとって、新しい人生の始まりを告げる重要なイベントです。
しっかりと準備をして、素敵なスタートを切りましょう。